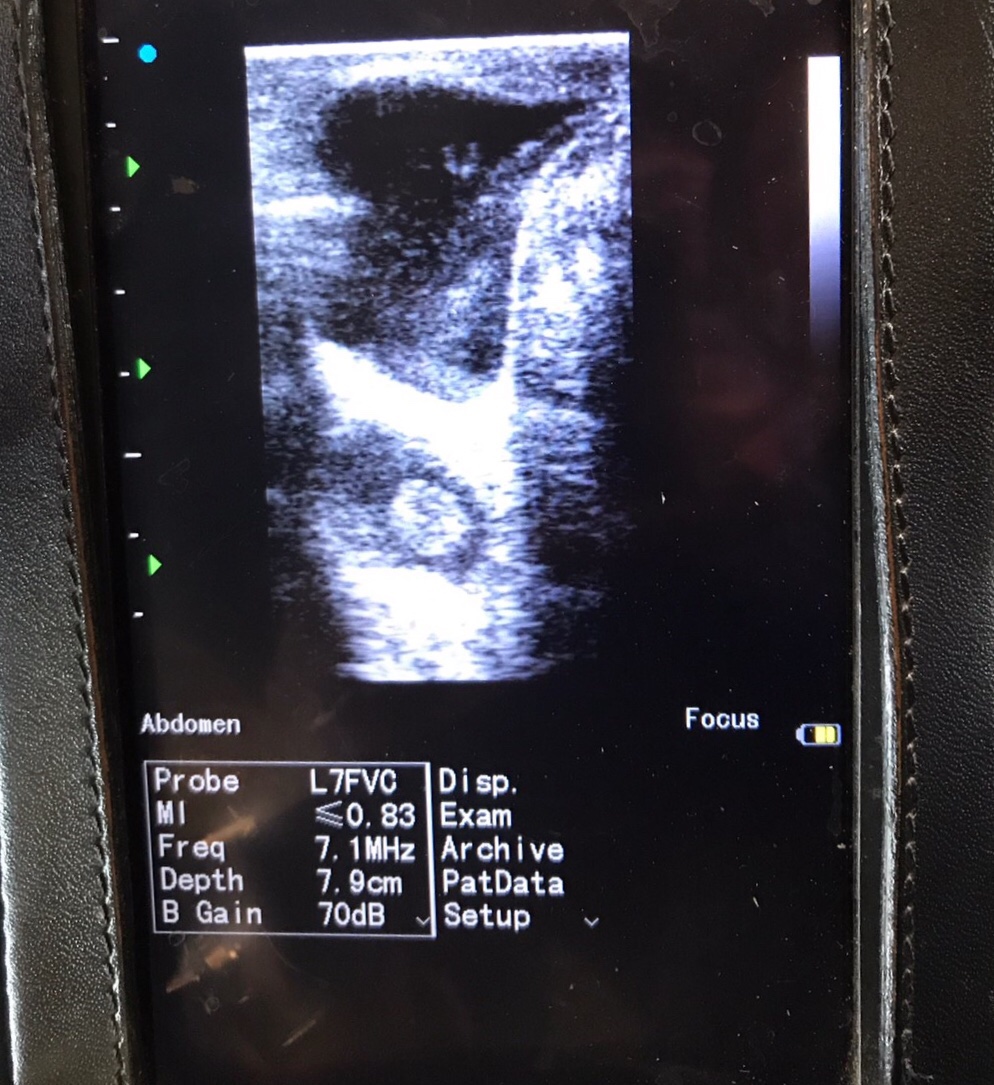山羊の削蹄講習会を開催しました
12月の終わりに山羊の削蹄講習会を開催しました!
地域の山羊生産流通組合さん主催の勉強会の講師を
ゆうきさんと院長先生とを務めさせていただきました。

今回のテーマは「山羊の削蹄」です。
(前回は「山羊の病気と繁殖について」お話しさせていただきました。)
山羊の蹄の構造と解剖について、削蹄の際に出血した場合の対処法、山羊の削蹄の基本と実際についてを実演講義
第1部では院長先生が
「山羊の蹄の構造と解剖について」と
「削蹄の際、出血した場合の対処法」についてお話しさせていただきました。
関連記事:
山羊の削蹄① 山羊の蹄の構造について
第2部ではゆうきさんが
「山羊の削蹄の基本と実際について」
実演をしながらの講義を行いました。
はじめはゆうきさんの削蹄の実演。

保定法や道具など、いろいろな質問が飛び交いました。
関連記事:
山羊の削蹄③ ~削蹄の道具~
次に、実際に参加者のみなさんに削蹄をしていただきました。


実際に、削蹄をしてみると足の持ち方やハサミの角度など見ているより難しい~。
でも、一緒にやっているうちに少しずつできるようになっていき
参加者の皆さんが笑顔になっていきました。
講習会をきっかけに「自分の山羊の削蹄をしてみる」との声
診療で、山羊舎に伺うと蹄が伸びすぎて歩きづらそうにしている山羊さんをよくみかけます。
講習会の終わりには「お家に帰って、自分の山羊の削蹄をしてみる」という声があちこちから聞こえてきました。
この講習会がきっかけになり、山羊さんの蹄の手入れに目を向けて頂ければ
うれしい限りです。
良いお天気の中、たくさんの皆さんに参加していただき、
終始、なごやかな楽しい講習会になりました。
削蹄講習会の資料は今後このブログでご紹介していきたいと思います。






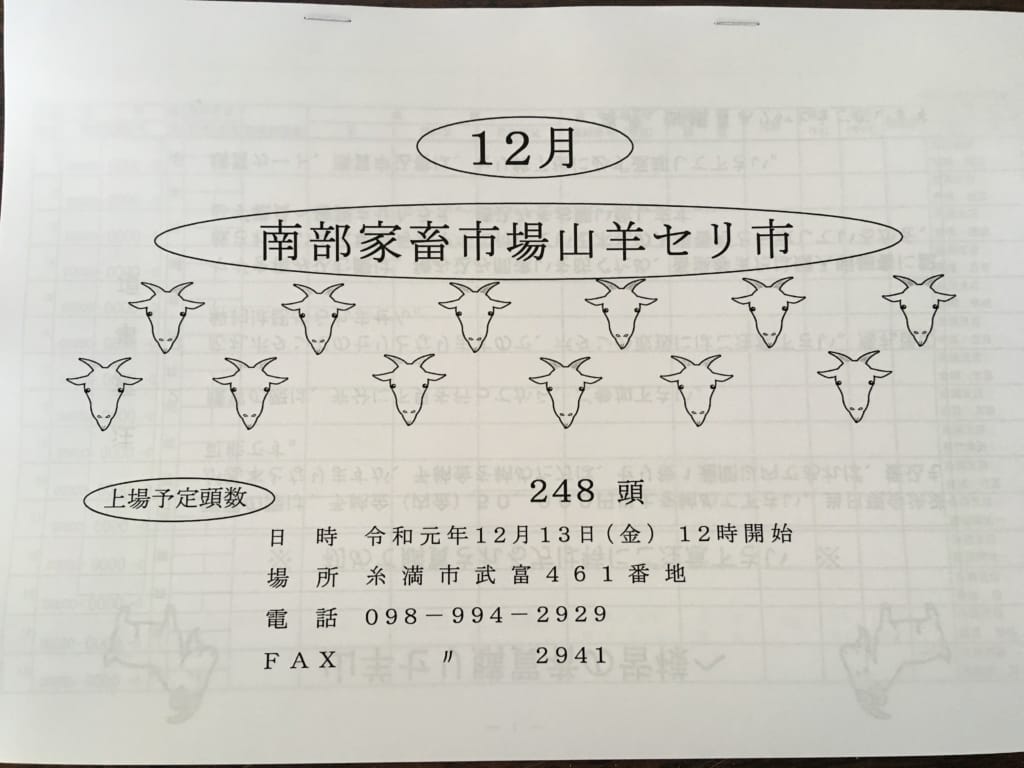






 茶色い山羊さんや大きい子から小さい子までほんとにいろんな山羊さんがいました。
茶色い山羊さんや大きい子から小さい子までほんとにいろんな山羊さんがいました。












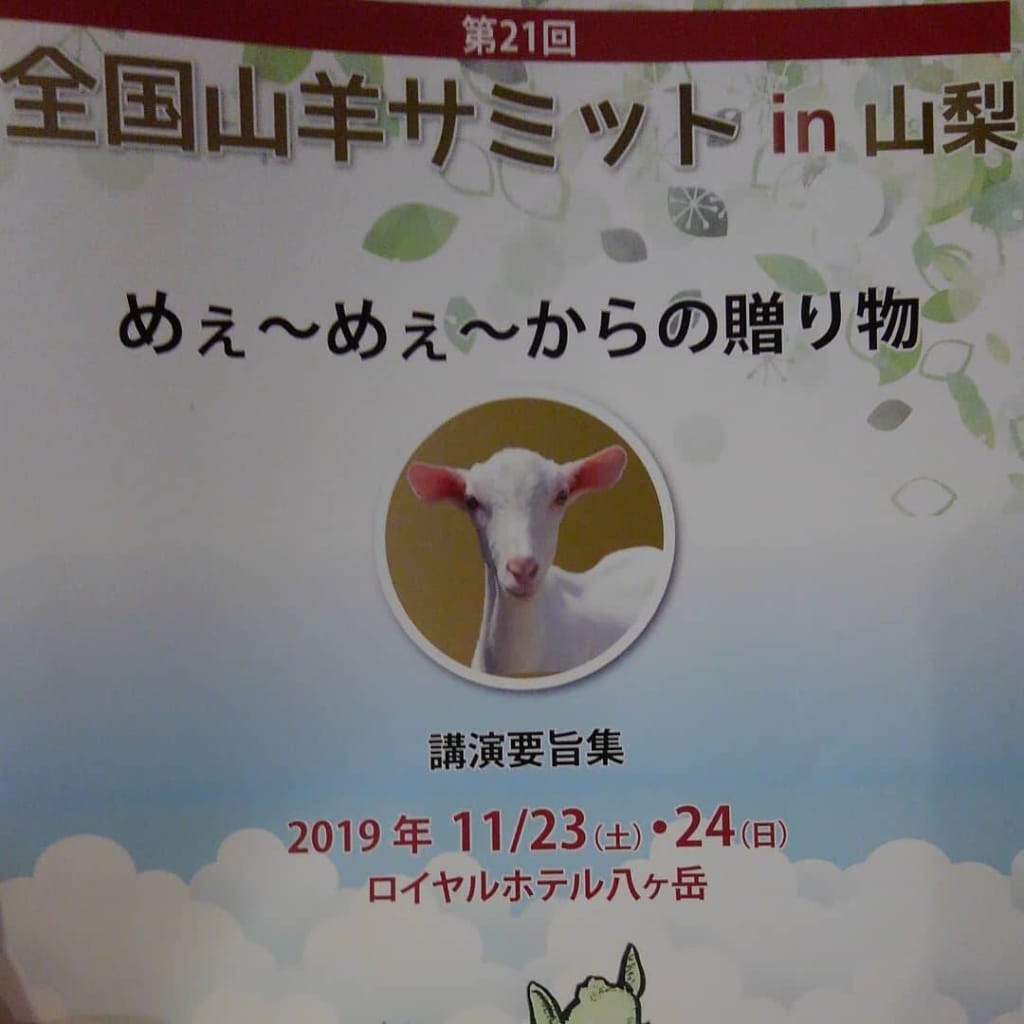


 全国の山羊の研究の先生方、山羊の飼い主様とお会いすることができ
全国の山羊の研究の先生方、山羊の飼い主様とお会いすることができ