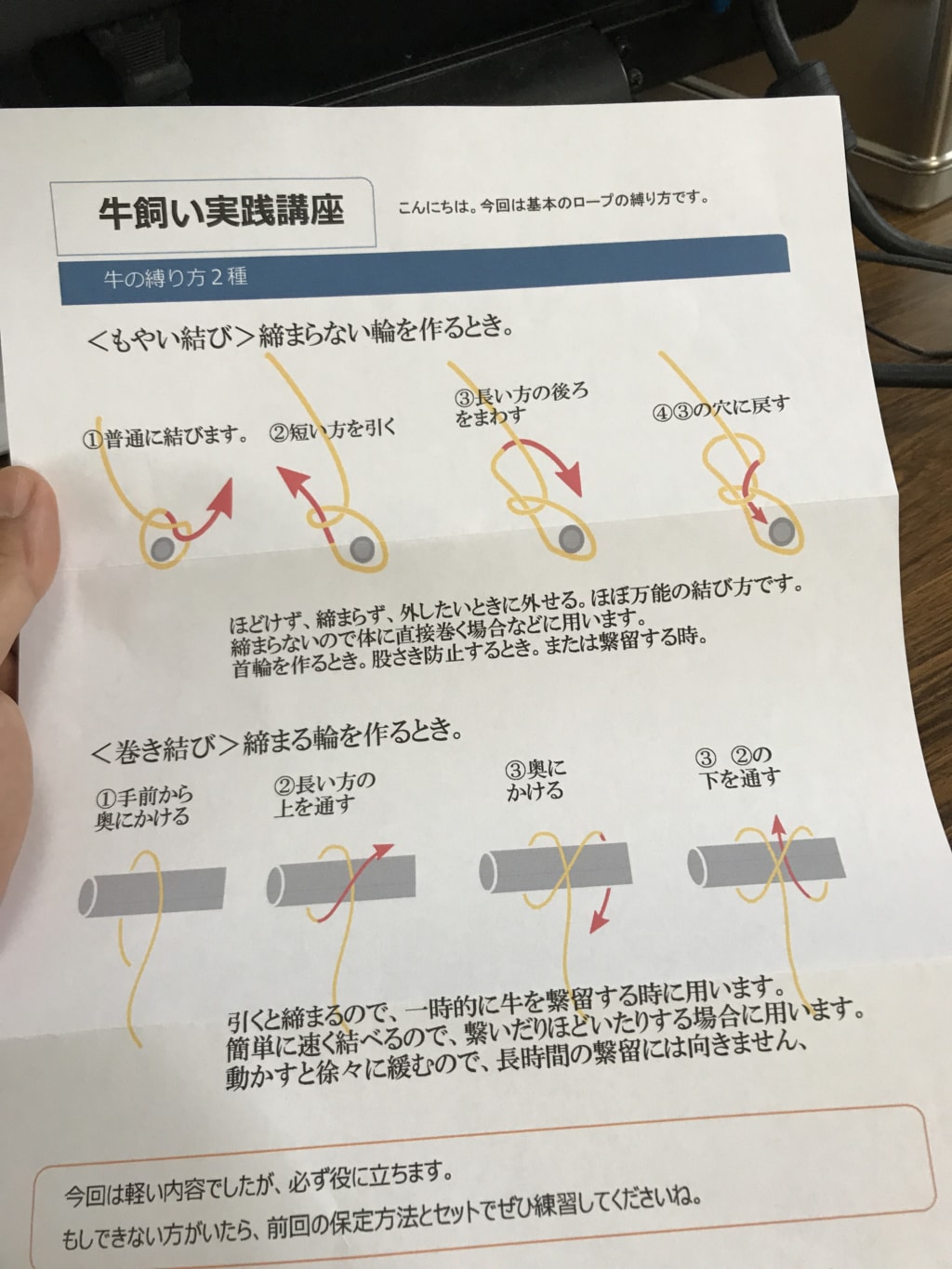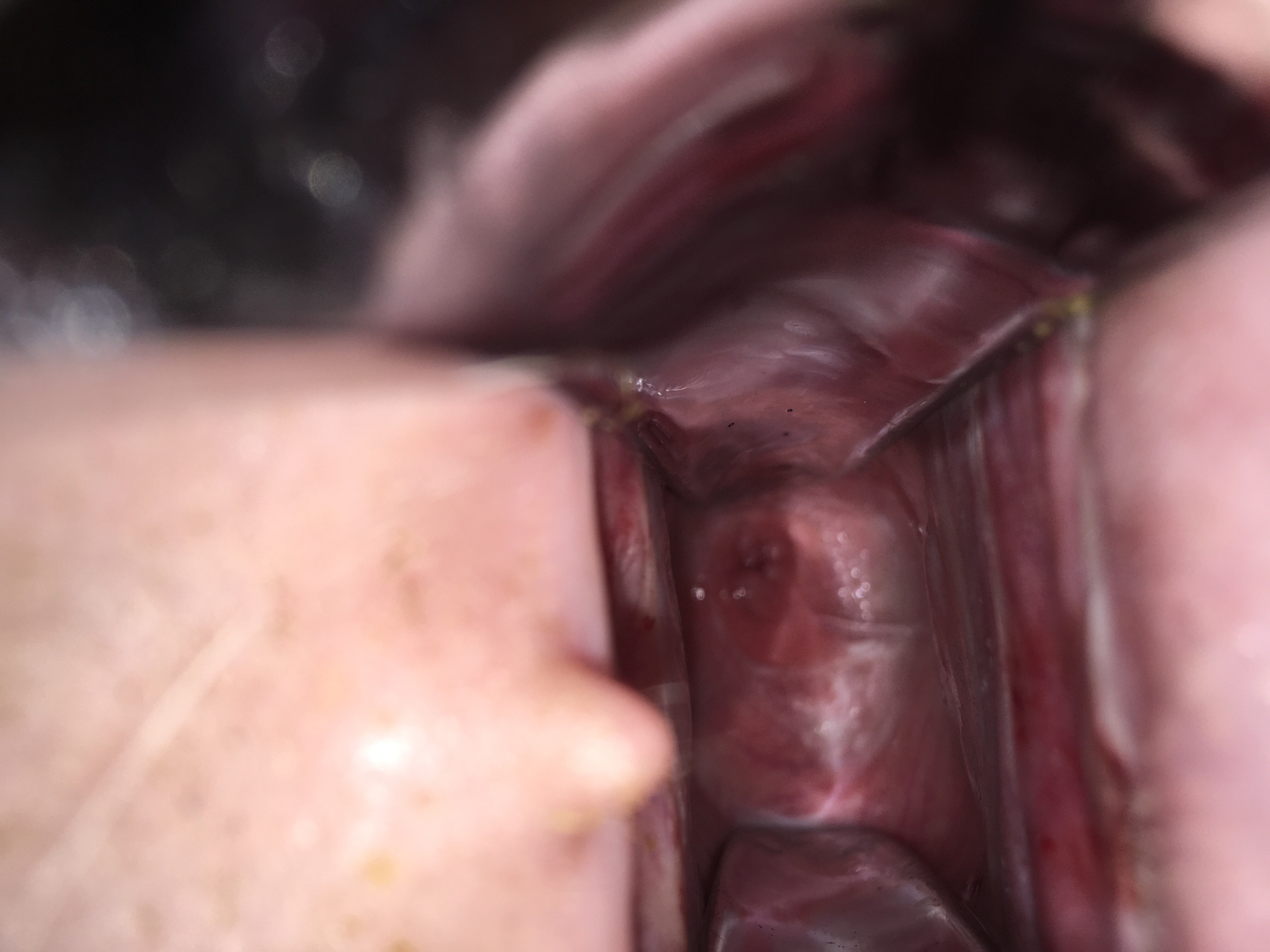*山羊の診療Diary 症例7 「出産後20日の下痢」
お母さん山羊のあめちゃんが朝、下痢をしているのに気がつきました。

山羊さんの便はコロコロ丸いのが健康なので、このように粒がなくなり固まっているのは
下痢をしていることになります。
さっそく、あめちゃんの診察スタート。
はじめに、ごはんをあげて様子を見てみました。草を口にはするものの食欲は前日より落ちていて、元気もいつもよりありません。
次に聴診をしてお熱を測ってみました。聴診で心臓や肺の音には問題はなく、熱は40.5℃と高めでした。腹部の触診と聴診ではガスがたまっている様子も見られません。おしっこは確認できました。
ヤギが下痢を起こす主な原因
ではいったいあめちゃんの下痢の原因はなんでしょうか?
通常、下痢を起こす原因として以下の原因が考えられます。
食餌性 中毒や過食、変質飼料など
感染性 ウィルス・細菌・寄生虫など
環境性 寒さやストレス(神経性)など
今回、問診から食餌性の下痢の可能性は低いと思われました。
次に感染性の下痢について考えてみます。
ウイルスや細菌感染は子山羊さんも大人の山羊さんも可能性があります。一方、コクシジウムなどの寄生虫は通常大人の山羊さんでは寄生していても問題にならないことがほとんどです。しかし免疫が低下したような時は注意が必要です。あめちゃんは産後でいつもより体に負担がかかり免疫力が落ちている状態です。そのため、寄生虫の下痢も可能性も考えられました。
最後の環境性ですが、何日か雨が降り続いている毎日だったのであめちゃんにとってストレスがかかっていたことも考えられました。
産後間もない時期は、免疫力が落ち感染しやすい状態。産後特有の病気も
そして今回の症例では「産後間もない」ということは非常に大切なキーワードになります。
先ほどもお話ししましたが、免疫力が下がっている状態なので感染がいつもより簡単に起こる状態です。また、産後特有の病気がいくつかあります。代表的なものに以下の病気があります。
①産褥熱
分娩時に産道の傷から細菌感染が起こりお熱が出ます。出産後、1~7日の間に起こることが多く、
発熱すると食欲がなくなったりおっぱいの出る量が減ります。免疫が下がるのでいろいろな病気にかかりやすい状態になります。
②ケトーシス
いろいろな原因がありますが(妊娠末期に栄養が追い付かない・ホルモンの失調・肝臓の機能の低下など)からだの中にケトン体というものがたまってしまう一種の中毒でです。ケトーシスになると食欲を落としてしまいますので様々な病気を誘引することになります。
③栄養不足
おっぱいを出すためにいつもより栄養が必要ですが、栄養が足りない場合も免疫を落として感染に弱い状態になります。
症状はひとつでも、原因は様々で動物の状態もさまざま。(院長追記)
※院長追記〈〈〈〈
今回の症状は「下痢」です。
上記のように、症状はひとつでも、原因は様々で動物の状態も様々なんです。ですから、
①あらゆる原因の中から可能性の高いものを推定し、それらに対する対策を取ります。あくまで推定なので、いろいろな可能性をカバーできるように考えます。どうしても原因を区別しないといけない場合は検査をします。
②動物の状態を観察して、体を元気にする対策を取ります。大雑把に言うと体の弱り具合をみるんです。緊急性が高いほど、この治療が大切になってきます。
〉〉〉〉
今回の山羊の下痢ケースでの治療内容
以上のことをふまえて・・・あめちゃんの治療を行いました。
・ごはんの改善(あめちゃんが好きなもの・食べられるものを探して食欲を増進させる・栄養不足を解消する)
※体を元気にする治療、ケトーシスの予防
・整腸剤をごはんと一緒にあげる。
※食餌性下痢の治療
・抗生物質・駆虫剤の投与
※細菌性と寄生虫性下痢の治療、産褥熱の治療
・脱水、食欲のないときは輸液を検討
※体を元気にする治療
・床の掃除
※環境性下痢の治療
幸いなことにあめちゃんは2日後には熱も下がり、食欲、元気もいつも通りになりました。
便も形になってきたので経過を見ることになりました。
このように大人の山羊さんの下痢でも、産後はいつもと体の状態が違うので、考えられる病気が増えてきます。
ただの下痢と思わずに出産後の経過も考慮して見てあげることが大切だと感じました。